デザイナー樋口賢太郎が
綴る日々のことです
今年の抱負
遅くなりましたが、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。
年始の恒例なのでいちおう今年の抱負を書いておきます。
昨年自分は50歳を迎えました。
まだ実感が追いつかず、ただの数字としてしか認識していないですが、客観的にみると50歳ってだいぶ大台に乗った感がありますね。
江戸時代ならばもう寿命が尽きているかもしれない年齢で、現在でも夕闇の影がひたひたと足もとに迫ってくる年齢でしょうか。
ただここでも書いたようにデザイナーは若ければいいというものではなく、年齢を重ねることで得られるものがあり、
スタンスによっては可能性も広がるのではないかとポジティブに考えています。
前提としてみずみずしい感性を保つことが大事になると思うのですが、
それと同時に、表現できる領域を積極的に広げていくことが重要だと考えています。
同じスタイルで表現をしていると、上達しその範囲での完成度は上がりますが、煮詰まり、自己模倣へと陥いる可能性も高くなります。
自分自身が飽きてしまわないためにも、(流行を追うのとは違いますが)移り変わっていくことは大事ではないかと。
もともと自分が働いていた会社の教育として、ストイックというかミニマリスティックな傾向があり、
そこからどうやって広げていけるか意識的に活動してきました。
ミニマルなデザインはそれはそれで魅力がありますが、当然目的ありきなので、
全部をまかなうこともできないですし、万能ではありません。
最初はモノトーンが多かったですが、色や模様などを扱うことをプロジェクトごとに設定し、
領域を広げられるにはどうすればいいのか、できないことができるようになるにはどうすればいいのか、デザインしてきました。
もちろんすべてが予定通りというわけにはいかないですが、コンパスでぐるっと描く半径が大きくなるように、
スタート時よりは表現の幅も少しは大きくなっているのでないでしょうか。
今後も自分ができることを少しづつ広げていければ、年齢には追いつかれずに済むのではないかと、楽観的ではありますが考えています。
あとは感性の保ち方ですね。これはまた別の投稿で書きたいと思います。
以上今年の抱負でした。
※和火やってます。
※作家活動のインスタやってます。
追悼
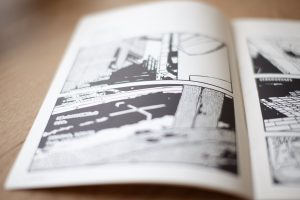
漫画家の魚喃キリコさんの訃報が届きました。
以前アートディレクションを担当していたフリーペーパーでお会いする機会があり、
贅沢にも描き下ろしていただきました。
気さくでフランクな方で、原稿料がないにも関わらず心よく引き受けてくださり、
充実した内容となりました。
漫画がそれまでと変わり始めた90年代を代表する重要な作家のひとりだと感じており、
端正で繊細な線でしか生み出せないオリジナルな表現は、その後の漫画を変える力を持っていました。
新しい作品を読むことができないのはつくづく残念ですが、いままでのを再読し続けることで、
その不在と欠落を少しでも先送りにできればと存じます。心よりご冥福をお祈りいたします。
金継と湿度文化 終

漆をはじめとする日本文化の多くは湿度とともにある。
雨なのか霧なのか分からない細かい水滴にびっしりと覆われた木々。
森の中に分け入れば岩は苔むし、水分を蓄えた森はまるで大きな海ように波打つ。
深呼吸すると微粒子となった水分が鼻と口から流れ込み、内と外の両側から湿度に満たされる。
ゆっくりと移動する霞の合間からは濡れそぼる蒼い山々が見える。
古くは長谷川等伯、近代では横山大観、現代だと写真家の藤井保らが表現している霧や霞などに覆われた風景は、
日本人の生理的感覚に訴えかけるものがある。
日本の表現者はかすかに水分子が混ざる大気の状態から、視界が真っ白に覆われる濃霧まで、湿度の違いを繊細に表してきた。
写真などを評して「空気感がある」と言う際にも湿度を表現していることが多いし、
日本画という言葉から連想する多くが山々に霞や霧がかかった風景ではないだろうか。

そこから見えてくるのは湿度への執着である。

日本人には乾燥した状態をネガティブに捉え、水気を帯びることをよしとする意識がある。
例えば気候的な事象だけでなく、精神的、物質的に満ち足りることを「潤う」というのは、
水分によってほとびることが何かを補うイメージと結びついているからだろう。
農業と水の関係を思えば、世界でも普遍的な感覚かもしれないが、日本の場合はもっと深くコミットしている。
美しさを表す言葉「麗しい(うるはしい)」は「潤う(うるほう)」が形容詞形に変化したものだ。
もともとが「水に濡れてつやつやと光沢のある、冷たい感じの美」(『古語大辞典』小学館)を 原義としているためか、
現在でもどこかしっとりとした響きを感じる。
「漆=うるし=潤し」も「潤う(うるほう)」の名詞形である。漆のつやつやとした光の集め方を見ていると、
言い得て妙と言うのか、 湿潤さ、潤沢さそのものが物質化したような錯覚を覚える。
古代では湿潤さと美しさに明確な境界線がなかったのかもしれない。


日本文化特有の「余白の美」も湿度によって培われたのではないだろうか。
手前から奥に行くにつれて濃度が段々と薄くなり紙白で終わる視覚表現は 霧、雲、霞などをその効果としていることが多い。
はじめは写実的な紙白だったのが、だんだんと意図的な白に変化していき、抽象的な余白に到達する。
濃霧が刹那に現れては消える環境が、 余白を「無」としてではなく「有」として捉える感覚を育てたと考えられる。

絵巻物などを区切る「雲霞形(うんかがた)」も湿度と関係している。
雲霞形とは、適切な呼び名がなかったので勝手に「雲霞形」と命名したのだが
雲とも霞ともつかないあいまいな形状により画面を分割する方法である。
絵巻物をはじめ屏風絵や掛け軸の四隅などにたなびいているので 多くの日本人には馴染みがあるだろう。
ストーリーの画面推移や時間経過の演出を容易にしたり空間を分けることに使われて来た。
当初は記号的な意味合いが強かったが、だんだんと絵画的な色彩を帯びていき、 空間的ダイナミズムを生み出す表現にまで発展する。
自由な曲線なので画面を大胆に分割することができ、 その後の日本独自の表現に大きく貢献したと思われる。

意匠化もされた。雲霞形が転化したと思われる霞紋は、 背景を必要とせずオブジェクト単体で成立している。
あいまいさのメタファーともとれる霞が、ここまでしっかりしたフォルムへとシンボライズされるには
高度な造形力と良質な伝統文化の両方が必要だろう。 雲、雪など他の湿度の状態も見ることができる。
宗教観とも切り離せない。
日本の宗教の根幹は霧や霞などの湿度と結びついている。
神道はその好例で、乾燥している状態よりも、しっとりと濡れた空気の方が「いる」という感覚になり、
柏手を打つ際により深いコミュニケーションができる気がしないだろうか。
それは神道のルーツが、森に由来するアニミズムと結びついているからだと思う。
水でじゅうぶんに潤うことは生命にとって理想的な状態だが、それは森も同じである。
豊かな自然に畏怖・畏敬の念を持ち、森羅万象に八百万の神を見出した神道が神秘性を最も獲得するのは、
生態系としての森が一番神々しくみえる時と同じだと思う。
鬱蒼とした森に発生した濃い霧は生命に豊饒をもたらし、森を切り開いた人間にも同じように恩恵を与えた。
現在ではそこから遠く離れてしまい、全身が濡れてしまうような濃い霧には覆われなくなったが、
目に見えない恩恵は途絶えることなく続いているし、古層を探ると日本人のルーツである森の記憶がよみがえってくる。
いまだ日本人の意識の奥底にはうっすらと霧が漂っているのだ。
<金継と湿度文化 1へ>
<金継と湿度文化 2へ>
図版出典(上から)
伊勢神話/宮澤正明
松林図(左隻部分)/長谷川等伯
bird song 伊豆沼/藤井保
氷図屏風/円山応挙
雑木林図屏風 /俵屋宗達
韃靼人狩猟打毬図屏風/狩野甚之丞
霞紋、富士山形、雨雲、山谷雪/『紋づくし』芸艸堂(霞紋を除く)
※この記事は2012年に投稿した記事の再掲載です。
過去のデータベースにアクセスできなくなったので一部加筆修正して掲載しています。
※和火やってます。
※作家活動のインスタやってます。
金継ぎと湿度文化 2

漆を用いて割れた陶片をつなぐ「金継ぎ」とは室町時代に始まったとされる伝統的な技法のことである。
漆を接着剤として用い、表面に金粉を蒔くことが多いので 「金継ぎ」と呼ばれているのだが、
主成分は金粉よりも漆などの含有率の方が高い。
金粉以外にも器の色や形に合わせて銀粉や真鍮粉を蒔いたり、あるいは全く蒔かずに漆で仕上げることもある。


まずは麦漆といって小麦粉と水と生漆を混ぜたもので割れた破片を接着させる。

乾燥後、目地を呂色漆で覆っていく。
水に強い呂色漆で表面をコーティングすることで耐水性を高めるとともに、 漆特有の滑らかな質感を与えることができる。
呂色漆が乾燥したら紙ヤスリなどで研ぐ。 塗りと研ぎの行程を何度か繰り返すことで漆は厚く滑らかになり、
やればやるほどその精度は上がっていく。
納得行く状態になったら、いよいよクライマックスの金を蒔く行程である。
呂色漆の上に接着させるためのベンガラ漆を塗り金粉を蒔く。

乾燥後、金粉をきちんと定着させるために薄めた漆を塗り、 再び乾燥させて磨き、ようやく完成である。
丁寧にやろうとすると全行程を終えるのにだいたい一ヶ月以上も要する、時代に逆行するようなとてもスローな技法である。

しかし時間と手間をかけて補修していると、なにか満ち足りない部分を埋めてくれるセラピー的な手応えを感じる。
おそらくこういう心持ちになるのは僕だけではないと思う。
日用品の多くが使い捨てですまされる昨今、 破損した一枚の皿をわざわざ補修することはめったにないだろう。
現代社会で賢い消費者といえば、新しいものを右から左に買い替える人のことを指すからだ。
基本的にメーカーは売るという方向性は考えるが、 メンテナンス及び修理という逆方向はあまり考えないので、
10年前に買った家電をなおそうと思っても、壊れた部品がメーカーに残ってることは少ない。
対象期間を過ぎた修理には多大なコストとエネルギーがかかり(買った価格より高い場合もある)
消費者は割り切れない気持ちで新しい商品を選ぶことになる。
修理すれば使えるものを破棄する罪悪感や居心地の悪さは、 新品の家電を買うことで紛らわせるしかない。
金継ぎはそのような行為のアンチテーゼとして浮かび上がる癒しなのではないかと思う。
もうひとつ感じるのは湿度との密接な関係性である。 漆は空気中に水分がないと乾燥しない不思議な素材で、
湿度が多いムシムシした日本の気候は漆を乾燥させるのに適している。
乾燥させる場合、室(ムロ)と呼ばれる温湿度を一定に保つ密閉容器に入れるが、梅雨時なら室なしで乾燥可能である。
漆とはご存知のようにウルシの木の幹を傷つけると滲み出る樹液のことで
触れるとかぶれるので危害を加える動物や人間などから身を守ることができる。
人間の血液と同じように幹の傷の修復作用もあるが、乾燥した地域では凝固しないので必然的に湿度がある地域を求めて植生する。
漆をはじめとする日本文化の多くは湿度とともにある。
<金継と湿度文化 終へ>
※この記事は2012年に投稿した記事の再掲載です。
過去のデータベースにアクセスできなくなったので一部加筆修正して掲載しています。
※和火やってます。
※作家活動のインスタやってます。
金継ぎと湿度文化 1

趣味というよりは病気なのではと諦めている自分の性癖のひとつに器蒐集がある。
もともと食べることが好きで、よりおいしく食べるためには、いい器が必要で色々と集め出した。
ちょっとした料理でも、それなりの器に盛りつければ、 さまになる経験はどなたでもお持ちではないかと思う。
大きく捉えると、食べることは五感の内のひとつだけを使うのではなく、
自分が置かれている環境の中で味覚も含めた他の感覚も総動員して楽しむ体験だと考えている。
なのでどんなにおいしい料理でも、適切でない環境や文脈で食べると適切でない味になってしまう。
6畳一間のアパートに置かれた小さな机で、名シェフが腕をふるった料理を食べてもおいしくないだろう。
キャンプという状況で、料亭の吸い物を、アルミのカップに盛りつけても充分に楽しめないだろう。
6畳一間やキャンプが悪いわけでなく(キャンプにはカレーのほうが合うだろうし)、
味覚を主体とした総合的な体験には、他の感覚も適切な状態であることが求められるからだ。

もう閉店してしまったスペインの名店「エル・ブジ」は 既存の料理を一度解体し、再構築する前衛的な手法で知られていた。
「ロズマリー風味の肉のロースト」を供する際には、 肉には香りを付けずに焼き、
ロズマリーから抽出したオイルを 客の周りにスプレーすることで料理を完成させる。
風味さえも再構築する大胆な手法にエル・ブジの神髄をみたような気がした (落語にもうなぎを焼く匂いでご飯を食べる話がありますね)。

器は環境を構成する一番重要な要素で、いい物だと料理が格段にアップする。
日本の器の多様性と品質の高さは、器蒐集をする者にとって恵まれた環境であろう。
本格的という観点で洋の東西を見比べてみると、西洋では皿をセットで揃える必要があるが、
日本ではその必要はなく、出自や脈絡を超えた集め方ができる。
センスさえよければ和懐石の席で年代と窯元が違う器を組み合せても問題なく
むしろその組み合せにこそ妙があると言うべきかもしれない。
このことは日本に於けるオリジナルな器文化が育つことに大きく関わっているし、
もしこの自由度がなければ、 現在でもこれだけ多様な窯元が日本に存在することはできなかったと考えている。

そろそろなんだかタイトルと本文が違うなと思い始めたかたもいらっしゃるだろう。
ここまでは自分の趣味を正当化するための言い訳で、 つまり日本にはいい器がたくさんあるので買いすぎて困ってしまうのだ。
民藝中心だけれども旅先でローカルな窯元があれば必ず立ち寄るし、 いい物であれば個人銘でも買い求める。
骨董の領域にも興味はあるが、権威や能書きとは無関係な分「民藝」の方が純粋に楽しめると思う。
ただこの趣味の問題はどんなに大事にしていても割れてしまう点だ。
眺めるだけではなく、実際に使うことが僕の器の楽しみなので 気に入った物ほどよく使い、比例して破損率も高くなる。


もちろん「花は散るから美しいし、器も割れるからこそ価値がある」のだろうと思う。
割れる「はかなさ」が内在しているからこそ大事にし、慈しみ、後世へと残そうとする。
もっとも日本文化には割れてしまった器でさえも、再びよみがえらせる方法がある。
知っている人は知っている「金継ぎ」という技法だ。
この技法は再び使える状態だけを目指すのではなく、 壊れたことをポジティブに捉え、価値を高めることを目的としていると考えている。
欠けや傷を同色ではなく、素材とは異なる金や銀などで繕うのはそのためだ。
数年前から始めた金継ぎが最近ようやくモノになってきた。
<金継と湿度文化 2へ>
※この記事は2012年に投稿した記事の再掲載です。
過去のデータベースにアクセスできなくなったので一部加筆修正して掲載しています。
※和火やってます。
※作家活動のインスタやってます。