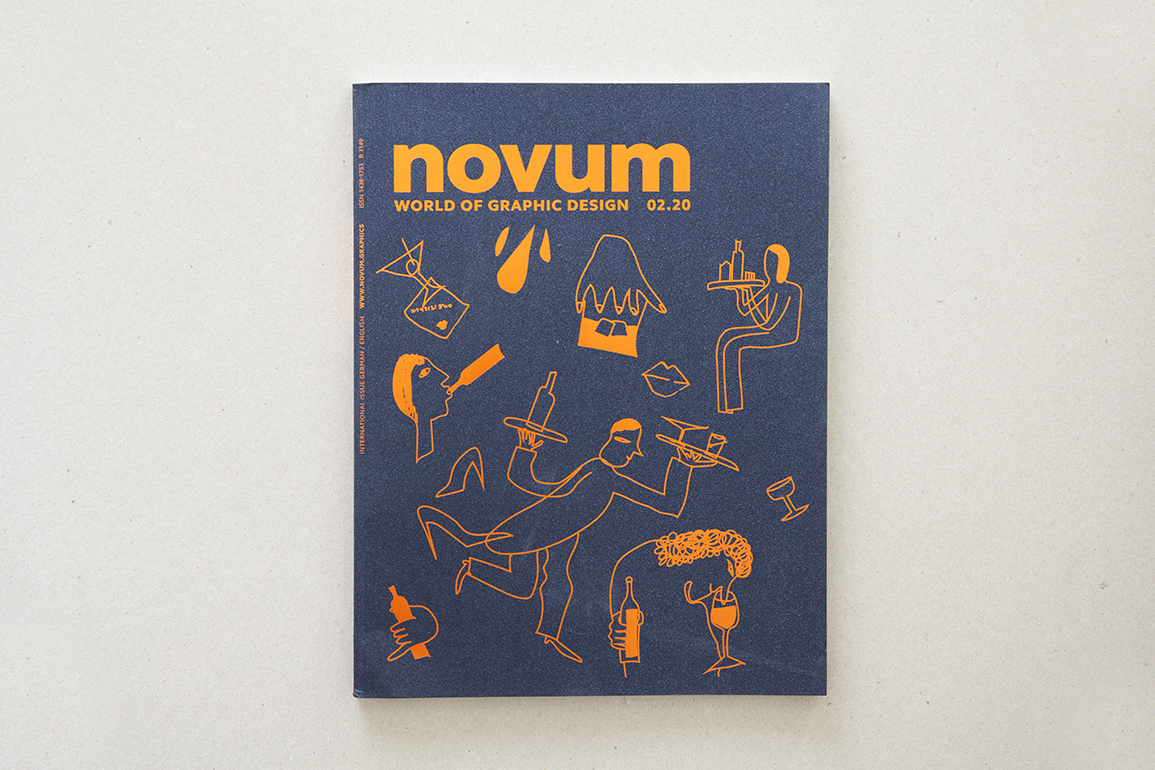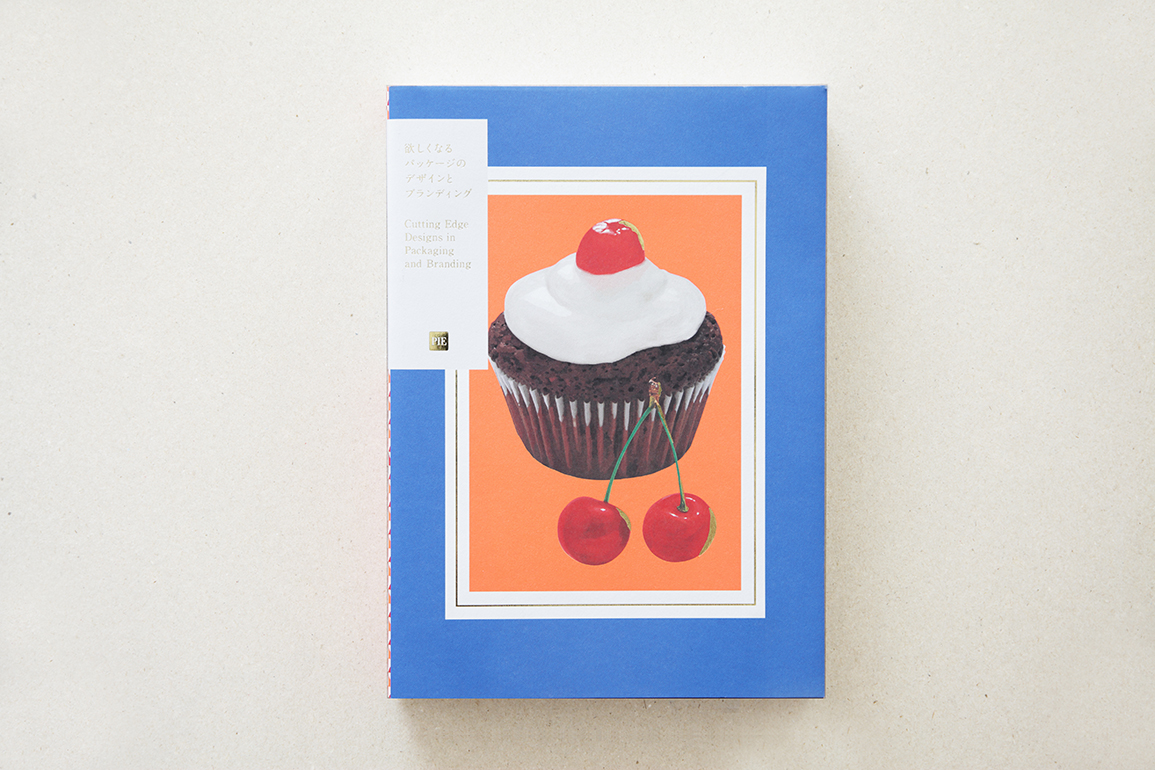デザイナー樋口賢太郎が
綴る日々のことです
コロナが奪うもの
まったく未知のウィルスが猛威をふるっている。
現実的な被害も甚大だが、おそらくコロナが一番やっかいなのは先行きが見通せない不透明さにあるだろう。
感染率が高くても、1年後には必ずワクチンができますとなれば、経済の見通しが立てられる。
死亡率が高くても、暖かくなりウィルスが不活性化するとわかっていれば、まだ人々の不安が拭える。
いまの世の中は、どれだけ正確に予測が立てられるかという、いわば確実性を元にまわっているので、
反対の性質を持つコロナは資本主義社会の経済がまわることを阻害する頭が痛い存在だと言えるだろう。
未知のものが社会をどのように変えていくのか想像するのは難しいが、ひとつだけわかってきたことがある。
それはインターネットがますます重要になるということである。
すでにさまざまなモノゴトがスマホを初めとするインターネットに吸い取られているが、コロナはこの傾向を急激に加速させている。
こう書いていると批判しているように思われるかもしれないが
まずはこのような状況にインターネットがあってつくづくよかったと考えている。
急速に拡がるコロナの情報を、時差なく世界中で共有し、可視化できることが、
有効な手立てになっているのは言うまでもない。
家に閉じこもっていても、SNSなどでやりとりできるし、映画や音楽を楽しめることが
どれだけ気持ちを楽にしてくれるか。ない状況を想像するだけでぞっとしてしまう。
中世ならいざ知らず、現代人でさえ疑心暗鬼になり、副次的に人を攻撃する事態が起こっているが、
インターネットがあるからか、魔女裁判までの悲劇にはつながっていない。
テレワークやオンライン授業などが始まり、今後それらがシステム含めて変わっていくのは間違いないだろう。
ただ現在のインターネットの使い方は、コロナ対策としては妥当だと思うが、
今後も通勤や対面の授業が必要ないものとして扱われるのは行き過ぎたことだと思う。
会社に毎日行くことの不合理さは前々から論議に上がっていたので、
このタイミングで在宅勤務になり、その恩恵を受けている人も多いかもしれない。
慣例として行われる必要ないモノゴトはとても多いから(例えばハンコを押すために会社に行くなど)、
そのあたりは刷新されて然るべきだと思う。
しかし全面的に通勤をなくし、会議や授業も全てオンラインで行えばいいという考えには組できない。
なぜなら現在の状況では、本当の意味で無駄なものと、一見無駄そうだが実は大事なものとの線引きができていないと考えているからだ。
仕事の合間にたわいもない話をはさむことで、本来の業務が円滑に進むこともあるし、
新しいビジネスのアイディアに繋がることもありうる。
長時間の電車通勤でさえ、オンオフの切り替えと事務仕事に充てて、
有意義な空間と時間を手にしている人もいるだろう。
例えば、会って話せる距離であれば、オンライン会議などせず、
対面で打ち合わせするほうが、短い時間でもクオリティが高くなると前々から感じていた。
2時間のオンライン会議より、30分の対面である。
それがなぜかは様々な理由があると思うが、
私たちが考えるよりもオンラインでやり取りできる情報量が少ないからだろう。
これも無駄の本質が腑分けできていないからだと考える。
学校教育に関しても何をか言わんやである。
N高などをはじめ、オンラインの新しい教育のあり方を模索することは有意義だが、
やはり対面や学生同士の横の会話が自由にできる学校教育に軍配があがるのは間違いないだろう。
なぜなら大学をはじめとする学校教育が提供できる最大のメリットは大いなる無駄遣いにあると考えるからだ。
それは時間の無駄遣いであり、エネルギーの無駄遣いであり、お金の無駄遣いでもある。
すぐに役に立たないということで、昨今大学の文系の予算が削られつつあるが、これも根源は同じ問題をはらんでいる。
いまは役に立たないが、10年後に、もしかしたら100年後に重要な意味を持つかもしれない学問を護する懐の広さが、
アカデミズムや大学が本来持っていた知性であり価値のはずであった。
現在の予算削減はヴァンダリズムに他ならず、無駄の本質を見極めないと、大事なことを見誤ってしまうのではと危惧している。
そしてその代償は50年後、100年後に払わないといけなくなる。
現在多くのモノゴトがインターネットを介することで、便利になったように感じている。
しかしいまだにインターネットは花の匂いも、手の温もりも、珈琲の苦さも伝えることはできていない。
コロナによって奪われる大事なものはたくさんあるが、自らそれらを捨て去らないように注意したいと思う。
まずは世間では無駄だとされているが、個人的に大事にしていることを守ることからだろうか。
※和火のインスタやってます。
※ただいまブログの引越し中です。旧ブログをご覧になりたいかたはこちらにアクセス願います。