デザイナー樋口賢太郎が
綴る日々のことです
マテリアリズムとは何か
今回家を建てるにあたって素材感を強く意識したということはここに書いた。
また桂離宮がモダニズムとは違う概念ではないかということも、以前中国から帰ってから考えていた。
素材を活かすことは、日本的な表現と密接に結びついており、建築だけでなく、
グラフィックデザインや工芸、料理の分野においても切り離すことはむずかしい。
いや、むしろ素材を活かさないで日本的な表現などできないのではないだろうか。
ややもするとひとは手を加えたくなる。
それは素材云々のまえに、プレーンな状態は、なにも仕事をしていないという意識に繋がり、
コミュニケーションとして成立しにくかった背景があるのだと思う。
世界的に見ると、装飾などが施してあるほうが売り買いのときにもお金を取りやすいし、
プレゼントするにしても、ああこんなに手が掛かった物をもらったと納得されやすい。
権威を示す際にも装飾があるとわかりやすいだろう。
しかし日本という非常に高いコンテキストのなかでは、
阿吽の呼吸のようなコミュニケーションが存在していて、その密度の高さが装飾的なものを遠ざけていたと考えている。
自然が豊かなことも強く影響していて、島国の独自の文化と環境が掛け合わさって
素材をエクストリームに尊ぶ、世界的にみても珍しい価値観が育成されてきた。
一方のモダニズムは基本的に機能性を求め、ミニマリスティックなアウトプットを目指す。
素材感が邪魔とまでは行かないが、無機質なマテリアルのほうが機能優先の価値観により合致する。
例えばグラフィックデザインで言えば、いわゆるゴシック体がモダニズム的な表現と結びついてきたのは、
書体の構成要素であるセリフが必要ないという、機能主義的な側面から判断されたからである。
ゴシック体の黎明期にはその無味乾燥さに拒否感を示すひとも多く、グロテクス体と揶揄することさえあった。
もちろん素材を生かしたモダニズム的表現もあるとは思うが、装飾的なもの伝統的なもの地域的なものなどを遠ざけることによって
モダニズムが成立しているとすると、素材というファクターはあまり重要視されて来なかったのではないだろうか。
桂離宮をはじめとする日本の建築様式はモダニズムとは異なり、素材の良さを表出させ、
顕在化させるために余計な要素を削ぎ落とす、素材主義=マテリアリズムなのではないかと思っている。
建築物に限らず、日本のデザインはシンプルとカテコライズされることが多いし、
ブルーノ・タウトも桂離宮をモダニズム建築としてヨーロッパに紹介したようだが、実際のところは似て非なるものではないだろうか。
日本刀と寿司と桂離宮は並列に比較することができると思うし、
コンクリートを主体的に扱う安藤忠雄が、日本から出現したのもこのマテリアリズムがあるからだと考えている。
週末から香港に旅行に行ってきます。文化大革命を免れた中国に興味があり、昨年は台湾を訪れました。
香港(厳密に言うと香港島)も本土にありながら直接的な影響を受けていないとされ、
数千年続いた中国の歴史が残っているかどうか見て来たいと思います。
※和火やってます。
※作家活動のインスタやってます。
追悼
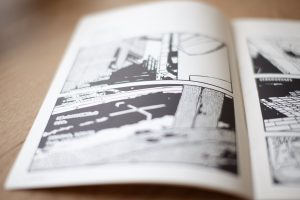
漫画家の魚喃キリコさんの訃報が届きました。
以前アートディレクションを担当していたフリーペーパーでお会いする機会があり、
贅沢にも描き下ろしていただきました。
気さくでフランクな方で、原稿料がないにも関わらず心よく引き受けてくださり、
充実した内容となりました。
漫画がそれまでと変わり始めた90年代を代表する重要な作家のひとりだと感じており、
端正で繊細な線でしか生み出せないオリジナルな表現は、その後の漫画を変える力を持っていました。
新しい作品を読むことができないのはつくづく残念ですが、いままでのを再読し続けることで、
その不在と欠落を少しでも先送りにできればと存じます。心よりご冥福をお祈りいたします。
苔むすお札


日本のお札を見ていると、そのイメージの基本となるものが、苔から来ているのではと感じるのは僕だけだろうか。
それは色合いでもあるし、意匠でもあるし、紙の質感でもあるのだけど、
なんというか全体として苔むした岩のようなものを目指してデザインしているように思える。
国家として、ある意味では一番信用を得ないといけない局面で、苔的なものが表出する不思議さを考えてみたい。
日本の中にいる分には苔っぽいと感じることはあまりなくて、海外旅行などで、オレンジ系や派手なお札を目にした時に、
「派手だとありがたみがないなあ」とか「もっと色調を抑えた方がお札っぽいのでは」と意識することから始まる。
見慣れたものが変わることでの違和感は差し引いても、日本人としては、
彩度が高かったり、色の組み合せが派手だと、お札としてはふさわしくないと感じるのだろう。
識別性という観点では、似た色調でない方が望ましいが、日本のお札はくすんだ色調の中からのみ選ばれていると思われる。
彩度が高い色を好まない傾向が日本にはあるかもしれないが、原色をそのまま用いるような伝統的な表現も少なくなく、
漁師が使う大漁旗などは気持ち良いくらいに原色で構成されているし、日光東照宮や伊藤若冲の絵などにもなんのためらいもなく使われてきた。

ド派手な色を好まない大和的意識の傍らで、南方系の原色を使う文化も脈々と受け継がれてきたのだ。
つまりパレットには様々な絵の具が出ているが、渋い色しか使っていないと思われる。
もちろん渋いだけでは苔っぽくはない。赤系や茶系でも緑系ベースの色調を保持していること、
その赤や茶が全体にではなく部分的に分布し、あたかも岩肌に自生する苔の様にみえることなどが主な要因だと思う。
面白いのは緑系ベースのみでまとめられている千円札よりも、一万円札などの緑系×赤系のミックスの方がより苔感が出ている点だ。
緑だけの色調だと、他の植物も想起するが 赤や茶色が混ざることで石を覆っている苔という状態が明確になるからかもしれない。
君が代は 千代に八千代に さざれ石の いわおとなりて 苔のむすまで
この歌の解釈はいろいろとあるだろう。
しかしいずれにせよ誰かの未来永劫の繁栄を願うことは共通していて、その比喩として苔が用いられている。
古来より苔は、日本人にとって「得難いもの」「かけがえがないもの」の象徴とされてきた。
苔を見るとき、人はいろいろなことを想像する。
その生育の遅さを考え、目の前に広がる面積を埋め尽くすには どれだけの時間がかかるのだろうかと。
その不可逆性を思い、どれだけ長く踏み荒らされていないのだろうと。
京都の苔で有名な西芳寺、いわゆる苔寺も、その面積を埋め尽くすのにどれだけの時間と労力を費やすかを
見る人に想像させて完結する部分があるだろう。
苔は特別な植物なのだ。
現在において手にすることができない最も象徴的なものがお金だとしたら、
苔を尊ぶ民族は、国歌や庭だけではあきたらず、紙幣にまで苔を生やしてしまったのだろうか。
◎写真協力
大漁旗の写真:女川みなと祭り|マイノートblogより
※この記事は2013年12月に投稿した記事の再掲載です。過去のデータベースにアクセスできなくなったので一部加筆修正して掲載しています。
※和火やってます。
※作家活動やってます。
京都
一瞬は永遠

その画家は言った。
一瞬は永遠だと。
一瞬が永遠になりうるのだと。
たかだか数十年しか生きていない人間の絵が何百年もの間、
人々を魅了し続けるのは不思議じゃないかい?
万物のエネルギーの法則からすれば、
費やした年数と消費される年数は同じになるはずなんだよ。
海に臨むアトリエは絵筆や描きかけの作品などで散らかっていた。
窓の外では狂ったように草木が揺れ、横殴りの雨が降っている。
黙って聞いていると画家はさらに話を続けた。
絵筆を走らせていると、自分の能力以上の表現が出てくることがある。
時代を超越した普遍的な魅力とでも言うべきか。
その瞬間に起こるのは、生きてきた年数を遥かに超えた
永遠とも言える時間の定着なんだ。
つまり一瞬のうちに永遠を定着することができる。
だから寿命以上に絵が残ることはなんら不思議ではないんだよ。
話はぷつりとそこで終わった。
嵐が近づこうとしているのか、風雨はさらに激しくなり、
舞い上げられた砂が窓ガラスにあたるパラパラという音が聞こえてくる。
ビデオの早回しのようなスピードで移動していく暗雲を見ながら、
画家が再び口を開くのを待った。
※この記事は2016年9月に投稿した記事の再掲載です。
過去のデータベースにアクセスできなくなったので一部加筆修正して掲載しています。
※和火やってます。
※作家活動やってます。







