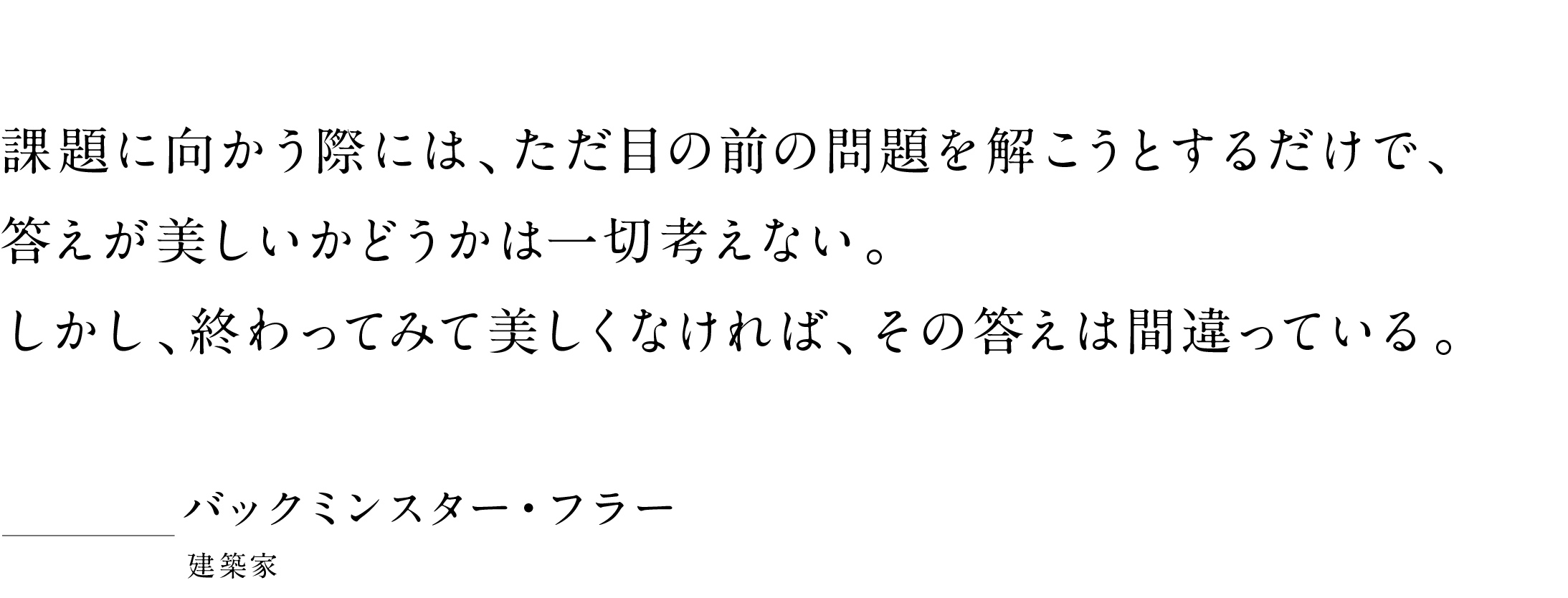デザイナー樋口賢太郎が
綴る日々のことです
誰のための掃除か
世界観のお話
課題に向かう際には…
どのあたりの人間か ?
都会人間か田舎人間か。仕事人間か生活人間か。
人って上記のようにざっくりと分類できるんじゃないかと前々から思っていました。
そんなに大したものじゃないんですが、なんとなく方向性に迷っている際には、少しは役に立つかもと思い投稿してみます。
最初の問いは自然が豊かなところに住むのが好きかどうか。
人って、ビルばっかりで人工的な環境に住むのが好きというタイプと、
緑が多いところに住みたいというタイプに大別できるのではないでしょうか。
理由はわからないですが、経験的にだいたいどちらかのタイプにわかれるようです。
そのことを都会⇆田舎という対義語で表しています。
もちろん都会⇆田舎には便利⇆不便など他の側面もあると思うのですが、
自然が豊かかという要素の方が支配的だと思っています。
おそらく自然に対する感覚って本能的なものなので、便利⇆不便などの合理的判断よりも上位に来るのでしょう。
この問いは、どちらがより健全かというようなことを現すわけでなく、ただの傾向をみるためのものです。
自然が好きな人のほうについつい健全な印象を抱きがちですが、そんなのただの趣味志向でしょう。
たぶん人の歴史って常に自然の脅威との戦いだったので
手放しで自然が多いほうがいいとは言えない部分があるのだと思います。
次は仕事人間か生活人間か。
簡単に言えば仕事が好きか、家事が好きか。
いままでは便宜的に男=仕事、女=家事という風に役割分担してきましたが
本質的には個人の特性なので、性別でわけないほうがみんな幸せになれると思います。
男でも料理や掃除をしている方が好きという人もいるだろうし、
そういうのは一切苦手で仕事だけしていたいという女性も一定数いるからです。
狩猟民族で言うと、狩りに行くのが好きなタイプと、家で待ってるのが好きなタイプ。
これらの分類わけでざっくりと自分はどっちなんだろうと考えておくと、ある程度方向性が見えてくるんじゃないでしょうか。
例えばタイプ的には家事が好きだけど仕事をしないといけない場合は
嫌々仕事をするのではなく、家事をうまく仕事と結びつけるほうがいいかもしれません。
料理とか掃除をプロレベルまで追求し、マネタイズすることもできると思うからです。
片付けコンサルタントの近藤麻理恵さんはその方向で世界的に成功してる人ですね。
あるいはもしその人がタイプ的に田舎人間だとしたら、家賃などのコストがかかる都会でなく田舎に住んで、
仕事の時間をなるべく少なくするという選択肢もあるかもしれません。
自分が食べる分は畑で育てるという選択肢もありですね。
逆に仕事だけしていたいという人は、掃除・洗濯・料理などは外注すればいいと思います。
仕事人間の場合は都会に住むほうがメリットがあるでしょう。
昔は住む地域や社会的な制度が固定化されていたので、まったく選択の余地がありませんでしたが、
近代化以降ではだいぶ自由に選べるようになってきました。
そういう意味で、新しく手にした自由を考えるための問いという見方もできるかもしれません。
自分はというと田舎人間で、後者は中間でしょうか。
現在は東京の世田谷区に住んでいますが、このエリアより都市部では生活できないです。
感覚的な境界線として、山手通りよりも内側になると、緑が少なすぎて息ができない感じになります。
後者の問いはデザイナーとしてはけっこう重要で、どっちかに行き過ぎている人はいいデザインはできないと思っています。
人がどういう風に暮らしているかわかっているからこそ有益なデザインを提示できるし、
ビジネス感覚も持ち合わせているからこそ、客観的な判断ができるからです。
生活から乖離しすぎてもいけないし、生活にどっぷりハマりすぎてもいけない。
これからますます民主的でリベラルな方向に世の中が進むことを考えると
どのあたりの人間なのか一度考えておくのは無駄じゃないかもしれないですね。
※和火のインスタやってます。
※ただいまブログの引越し中です。旧ブログをご覧になりたいかたはこちらにアクセス願います。
オタクで変態な日本人
まえまえから日本人の本質とはなにかと考えていた。
過労死するくらい働いたり、融通がきかず真面目だったり、あるいは本音と建前を使い分けたりと、
いろいろと外の国の人から揶揄されてきたが、最近は表題のように「オタク」と「変態」という2つの要素が
本質なんじゃないかと思っている。
オタクとは、要するに部分に固執する性質のことだ。
全体を俯瞰するのではなく、ディティールについつい目が向いてしまう。
広い分野を横断的に渡り歩くよりも、ひとつの専門性を掘り下げたくなる。
最初はアニメやフィギアなどを修飾する言葉として使われ始めたが
基本的にはあるジャンルへの視野狭窄の状態を指していて、
その言葉が生まれるずっと前から似たような気質を日本人は有していたのだと思う。
iPodの裏の鏡面磨きやナノサイズの注射針をつくるなど
ディティールを極めることに関しては他の追随を許さない。
なぜそのような気質なのか勝手気ままに論じれば
おそらくひとつに稲作文化の影響があるのだろうと思う。
田んぼに稲を一本一本等間隔に植えていく作業は、細かな神経を育むことを可能にし、
意識がディティールに向かう傾向を生む。
加えて国土面積が少ないということも関係していると考えられる。
日本では基本的に「小さいことは良いこと」という考えがベースにあり、
ウォークマンから車までコンパクトにつくられてきた。
それは限られたスペースを活用しないといけないからで
「大きいことは良いこと」という大陸文化が生んだアメ車のコンセプトとはだいぶ違う。
田植えもそういった合理性が関係しているとすると、国土の狭さがオタク気質を育む要因になったのだろう。
変態とは、「方向性の特殊さ」だと思う。
グローバルに見れば、日本の鉄道ダイヤの正確さは稀有であるし、
掃除がすみずみまで行き届いている状態は潔癖である。
海外から訪れた人は、日本人が手づかみで食事をするわけでもないのに、
なぜ食べる前にお手拭きを使うのかわからないらしいし、
出発が数分遅れただけで詫びる列車内アナウンスは、世界ではニュースとして取り上げられる。
正確さと清潔さはもちろん悪いことではないが、グローバルに見ればかなり偏向しているのは間違いない。
その理由のひとつに島国という地理的な要因が関係しているのだろう。
情報がシャットダウンされやすいので、文化的にガラパゴス化してしまうからだ。
これが陸続きであれば他国から干渉されるので、特殊な方向に進んでも、ある程度の客観性は保たれやすい。
しかし海に囲まれていると、知らず知らずのうちに、一般性を欠いたエリアに流されてしまう。
さらには日本は鎖国までしていた歴史があり、他国に支配されたこともほぼないので、
純粋培養に近い形で変態性が保持されてきた。
そういった土壌が日本のユニークな文化を生んだし、現代でも変態でいることを社会的に容易にしていると思う。
ガラパゴス化しやすい弱点を除けば、上記の気質は価値をつくることにとても向いていると思う。
変態性はオリジナリティを生む豊かな土壌であるし、オタク気質はそのオリジナリティを磨くスキルに繋がることが多いからだ。
しかし現在は価値がガラパゴス化してしまい力を発揮できていないと感じる。
得てして変態やオタクの人々は自分たちが特殊であることに気づきにくい。
まずは日本人が変態でオタクであると認めることから物事は始まるのかもしれない。
※和火のインスタやってます。
※ただいまブログの引越し中です。旧ブログをご覧になりたいかたはこちらにアクセス願います。