デザイナー樋口賢太郎が
綴る日々のことです
引っ越しました




年始にお伝えしていましたように、鎌倉に移りました。
工期が遅れていたのと、内装を部分的にDIYでやっている関係で、予定よりも時間がかかってしまいましたが、
今月のはじめ頃に引っ越しました。
まだまだ未完成を残していますが、住みながら少しづつ完成させていこうと考えています。
今回の家づくりで意識したのは、日本的な建物にしたいということ。
◎素材コンシャス
◎シンプル
◎地域性
これらの3つの要素を日本的と捉え、指標としました。
素材コンシャスとは茶の湯から続く、日本人独特の素材に対する感性で、もともとは千利休が見出したと考えています。
自然が豊かな環境で育った日本人のDNAには素材を尊ぶ感覚が刻まれているのではないでしょうか。
例えばそのことは、寿司屋のカウンターが、白木の一枚板でつくられていることに象徴的に表れています。
諸外国であればペンキを塗ってしまうところを、あえてそのままを楽しむ。
今回建てるにあたって、RC造を選んだのですが、それはコンクリートという素材を最大限に活かそうと考えたから。
木材の素材を活かす在来工法の選択肢も考えましたが、高気密・高断熱の面からRC造となりました。
なるべくたくさんの素材を使うことも意識しました。
コンクリート、石、木、紙、金属など素材が豊富な切り口も日本的だと考えています。
そして大事なポイントとしては塗装をしないということ。
塗装してしまっては素材感が活きません。
黒色が欲しいと思ったら、黒の石材を使う、茶色が欲しいと思ったら木材を使う、など
色を塗装で表現しない建物としました。
(木材などを保護するためにオイルやウレタンを塗布することなどは例外です)

シンプルとは素材感を活かすということ。
せっかく素材を活かそうと思っても、白木のカウンターが
レリーフでびっしりと埋め尽くされていると、素材の良さを享受しにくくなります。
桂離宮をはじめとする日本の伝統建築がなぜシンプルなのか、その答えも素材を活かす必然と考えると見えてこないでしょうか。
シンプルさと素材感は表裏一体の関係にあると考えています。
居住する地域にはそれぞれの気候風土や文化があります。
沖縄と北海道では当然求められる機能が異なるため、同じ建物を建てることはできないでしょう。
あるいは無理やり建ててしまっても快適ではないと思います。
その地域での快適さを素直に追い求めていくと自ずと地域性が出てくると思います。
以上ひとつでなく、3つを掛け合わせることで、日本的な建物が出現すると考えています。

そして総合的には、新聞社が年末にくれるようなカレンダーを壁に貼っても成立する建物を、ひとつの理想としていました。
カバーを付けない剥き出しのティッシュをそのまま置くということでもいいですが、
調和を求めすぎず、雑多に暮らしても受け入れてくれる懐の深さがあるという意味合いです。
どうやったらそういう建物をつくれるのか建築家に相談したところ、
構造を見せられる建物になっているか、そしてその構造を見せているかではないかと解答いただきました。
例えば合掌造りの家は新聞社のカレンダーを貼ってもビクともしないでしょう。
なぜならば構造を見せる前提で手を抜かずつくられているからです。
逆にいま現在量産されている経済性を優先した家は、プレカット材をボルトやネジで締めるだけだったり、
接着剤やタッカーなども使われており、躯体をあらわにはできません。
やみくもに構造を見せればいいということでもないと思いますが、機能美である梁や柱が露出しているほうが、建物として魅力的に見え、
そのことが懐の深さに繋がるのではないでしょうか。
構造をそのまま見せることができるからというのもRC造にしたひとつの理由です。
未完成なので全体をお見せできないですが、できあがったらまたアップしたいと思います。
※和火やってます。
※作家活動のインスタやってます。
アイデンティティとオリジナリティ(の続き)
前回の話に続いて、グローバル化する世の中において、
どのようにアイデンティティを築いていけばいいのだろうか。
生まれ育った歴史と地域に縛られると前回書いたが、膨大な質量の情報がやりとりされる現代において、
アイデンティティの厳密さを問うことはなかなか難しくなっている。
いま現在、日常的に和服を着る日本人はほとんどいない。
ハレの舞台である非日常着としては存在するが、だいたいは洋服を着用している。
あるいは日本語のコミュニケーションにしても同じようなもので
この文章の中にどれだけの外来語があるだろう(そもそも漢字も外来語だし)。
これはもちろん日本だけに限ったことではなく、世界で同時的に起こっていて、
日本に欧米文化などが流入する代わりに、和食やアニメなどが海外に浸透していっている。
ニューヨークでも北京でもロンドンでも日本と変わらない美味しいお寿司を食べることができるし、
漫画やアニメはおそらくいま全盛期を迎え、世界中で楽しまれていると思う。
日本に一度も行ったことがない西洋人が、日本人がつくるよりも美味しいお寿司を
提供していることもあるだろうし、そういった例も今後増えていくに違いない。
文化は誰でもアクセス可能なので、日本人もHIPHOPを歌うし、黒人の和食料理人も存在する(だろう)。
ただ文化は歴史と地域の掛け算であることからは逃れられないので、文化の本質を理解しているほうが、
より質の高い表現ができるのは確かだと思う。
寿司の本質を知っていないと、なぜ魚介類とネタを合わせるのかがわからない。
牛肉を乗せたものは寿司なんですか?日本にもそういったメニューはあるのですか?
とお客さんに聞かれたときに、きちんと返答できないと、信頼も得られないだろうし、
自分自身にも迷いが生じて、フルスイングするような大胆な表現は難しいだろう。
それは日本人が寿司を握るときでも同じことで、どれだけ本質にコミットしているか、その深度が重要なのだと考えている。
よくむかしから日本人にロックは歌えるのか?という論争があるが、
本質を理解しているのならば歌うことはできると考えているし、日本語の歌詞でもロックの表現はできる。
それはHIPHOPに置き換えても同じことで、ニューヨークのブロンクスとは違ったリージョナルな解釈もできると思う。
ただ上記で書いたように、西洋人と比べてどうしても分は悪くなってしまうし、
なぜ日本人がHIPHOPをするのかという根本的な理由も必要となってくる。
本質にコミットできる条件として、日本人ならば外国人よりも日本文化にアクセスしやすいし分、
有利であるというのが基本的な考え方で、その有利さのうえにオリジナリティを築いていくのが自然な流れではないだろうか。
日本的なデザインの本質は何なのか問い続けること、そして頭でっかちではなく、
その答えがきちんと感覚的に表現されていること、そういったことをデザイナーとして日々心掛けている。
※和火やってます。
※作家活動のインスタやってます。
アイデンティティとオリジナリティ
デザイナーとして活動しはじめた当初より、生まれ育った地域や文化は、大きなテーマだった。
ひとことで言ってしまえば「日本」ということになるのだが
最近はその言葉が持つ意味合いに、政治的あるいは思想的な違和感を感じるようになり、
いまのところは「地域的」という表現のほうがしっくり来ている。
(伝統や神道、あるいは夫婦別姓などという言葉が安易に保守や左翼などと結びつくようになり
軽々しく使えない状況はいつまで続くのだろう。ひとは一面的には語ることはできないので
当然保守的な部分もあるし、進歩的な面もある。言葉が歪んでみえるのは時代が歪んでいるからだろうか)
閑話休題
歪みはともかく、日本をテーマとして考えるようになったのは
学生時代の恩師佐藤晃一先生との出会いからであった。
大学3年生のとき「日本」をテーマとしたポスターをつくりなさいという課題が
佐藤先生より与えられ、あまり意識しなかったことに向き合うようになった。
学生の頃はどちらかと言えば、国籍を感じさせない表現に惹かれていて、むしろ欧米に目が向いていた。
デザインという言葉自体が外来語なので、西洋を向いている方が自然だったし、
ポスターなどで文字を扱う場合もアルファベットの方がしっくりきた。
そんな具合だったので佐藤先生の課題はどうやって取り組もうかと思案した。
作品をつくることは、花を育てることに似ている。
種を蒔き、なるだけ美しい花を咲かせるように養生していくが、そもそも土壌が豊かでないと芽は出ない。
意識したことがない分野は、土壌がやせていてガチガチに固い状態であることと同じなので
耕すために鍬を持つところから始めなくてはならない。
逆に常日頃から意識して、考えている分野は、ふっくらと柔らかく耕されていて栄養分も豊富なのだと思う。
志が高いデザイナーは、いつでも種を蒔けるように、空いている畑でも手を入れていることが多い。
課題は最後の最後まで苦しんだが、結果自分でも納得いく仕上がりとなった。
先生にも高く評価していただき、以降自分と日本との関係性をはっきりと意識するようになった。
東洋>東アジア>日本>東京。自分がいる場所はこのように認識していて、
この横軸に、伝統や歴史という縦軸が掛け合わされる。
もし自分のルーツに外国の血が含まれていたら、また軸が複雑になる。
いわゆるアイデンティティということになるが、オリジナリティはアイデンティティと不可分で
なにかしらの表現をしようと思った際には、まずは出自であるアイデンティティの確認が求められると思う。
日本のアイデンティティの上にしか、日本のオリジナリティは花開かないし、
フランスのアイデンティティの上にしか、フランスのオリジナリティは花開かないからだ。
そして地域にしばられない完全に無国籍な表現はないと思っている。
幸いにも日本は様々な文化の土壌が豊かで、デザインに関してもオリジナルな表現を探すことができる。
佐藤先生の課題は、自分の足元を見て、その豊かさに気付くことをひとつの目的とし、
自国の文化にしっかりと根を下ろし、養分をしっかり吸い上げられると、息の長い制作活動が可能になることを教えてくれた。
日本人としてのオリジナリティを深めて行く先に、個としてのオリジナリティがある。
最近はシンプルであること、素材コンシャスであることが個人としての大きなテーマである。
※和火やってます。
※作家活動のインスタやってます。
今年の抱負(というか、ご報告)


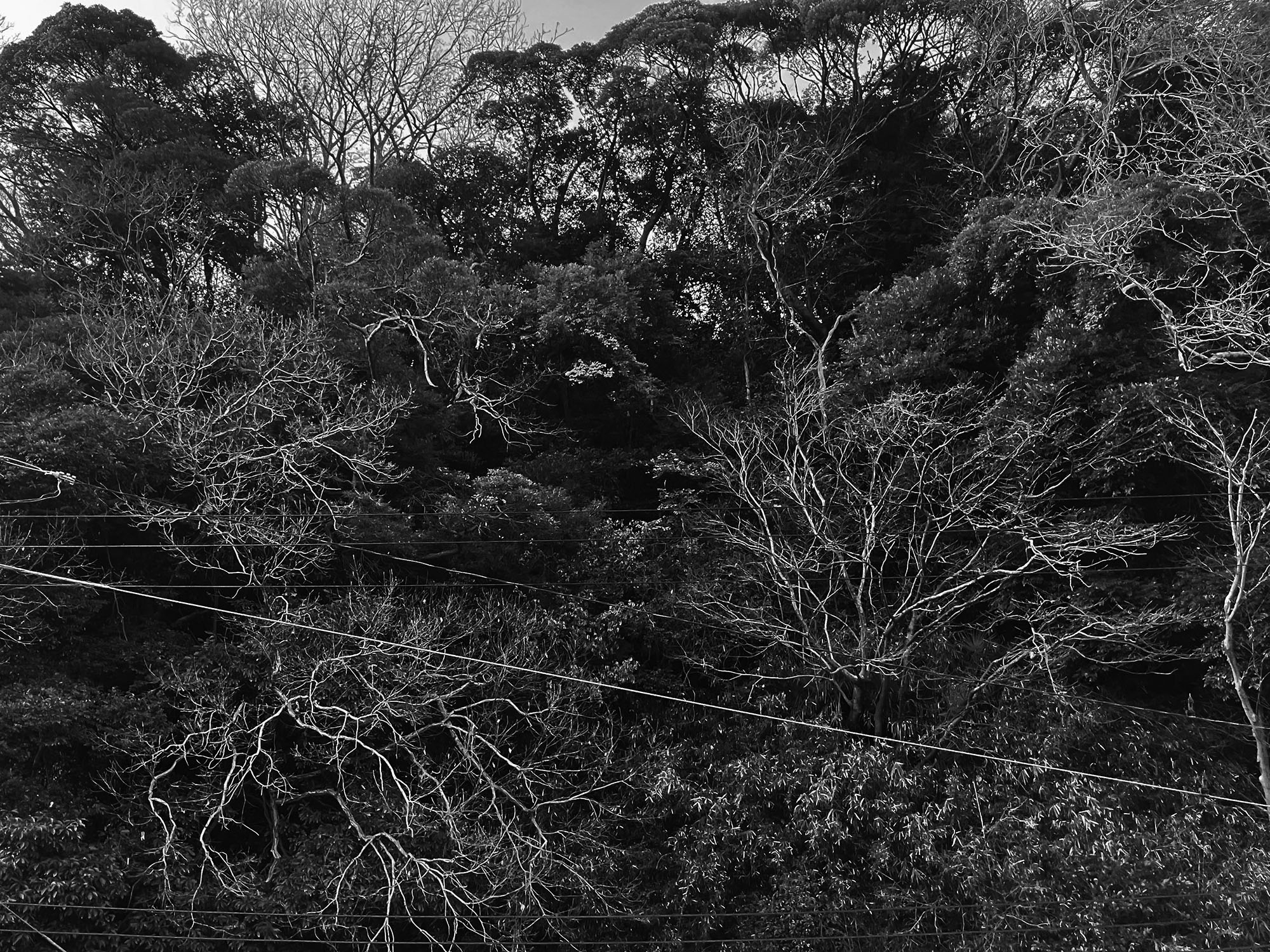
本年から鎌倉のほうに事務所を移転いたします。
土地を購入し、時間をかけて建築計画を進めて参りました。
いま拠点としている世田谷区は緑も多く、利便性も高い環境なのですが、
もっと自然を感じられる場所で暮らしたいという本能的な感覚がだんだんと強くなり、
事務所+自宅が建てられる土地をいろいろと探し回っておりました。
山だけでなく海もあるのが鎌倉を選んだ理由です。
そういった環境が与える影響がどのようなものなのかわかりませんが
自然が近くにあることで得られる豊かさをデザインに反映し、
よりクオリティが高い仕事をしていければと考えております。
家を建てることははじめての経験で、当然積もる話はたくさんあります。
コンセプトというか、どのような方針で考えていったのか、
その内容はまた別の機会に譲ることとし、転居の報告とさせていただきます。
すいせい
樋口賢太郎
※和火やってます。
※作家活動のインスタやってます。